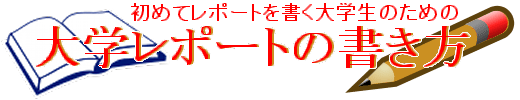レポート課題の本を読むときの注意点
大学のレポートはとても重要です。
そのレポートの中身で単位が取得できるかどうかにも関わってきます。
今回は、教授が指定した本についてまとめるタイプのレポート課題を例にとって説明したいと思います。
まず問題提起を読む
まず本を全部読むのではなく、出だしの問題提起をしているところだけを読みましょう。
そして著者の意見を知る前に自分の意見を簡単に考えておくのです。
そのあと著者の意見を読むことで、自分の意見とどのように違ったかわかるようになります。
また問題提起の答えを自分なりに推測することで本全体の中身が頭に入りやすくなります。
ただ漠然と本の内容をまとめるより、自分の意見と著者の意見を比較することで、
伝えるべきことが明確になり、レポートがスムーズに作成できるのでおすすめです。
教授の指定した本が難しく感じたとき
「この本についてまとめてきて」と言われたときに
指定された本の内容があまりにも難しいことってありますよね。
そんなときのレポートの書き方です。
このときに、絶対やってはいけないことは、ネットで本の解説や要約を探して写す行為です。
コピーアンドペーストは教授がレポートをチェックする際に1番嫌がることですから、
万一バレたら即落とされてもおかしくありません。
ではどうすればよいのか。
答は・・・降参するのです。
と言っても、あきらめてレポートを提出しないわけではありません。
具体的にどのようにわからなかったかレポートの中で説明するのです。
この時、どこがどのようにわからないか、細部まで書くことがポイントです。
分かったところと分からなかったところの線引きをはっきりさせましょう。
そうすることで教授はよく読み込んでいると捉えてくれるでしょう。
単位取得を前提に考えたとき、コピーアンドペーストより断然こちらのほうが安全策です。