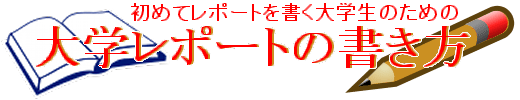実験レポートの注意点
教科書の丸写しは避ける
教科書を読めばわかる点については、読む方も疲れるだけなので繰り返さない。
ただし、まったく言及しないのもよくないので簡潔にまとめて書くとよい。
(教科書で3ページにわたって書かれている実験手順を5,6行でまとめるなど)
実際に行った方法と観察事実を「正確に」書く
名誉欲に振り回されて、ウソの内容を書いてはいけない。
うまくいかなかったときにも、「なぜうまくいかなかったか」を考察して今後の展望を書けばきちんと評価してくれる。
実験の目的、方法、結果、考察などを【項目ごとに】書く
実験目的は単語ではなく文章で。
レポートを書きやすいように、方法と結果をまとめて書いたり、結果と考察をまとめて書いたりしてもよいが、方法と結果と考察をすべてまとめて書くのはNG。
過去形か現在形か、時制に注意する
方法、結果は(事実なので)過去形で、考察は現在形で書く。
それ以外の部分についても適切な時制を使うようによく考えること。
データ、図、表をうまく使う
文字ばかりだと疲れるので、データや図・表・グラフなどで視覚的に訴える。
データを記した表+その表をグラフにしたものがあるとよい。
図や表には、表番号とタイトルを書くこと。(例:表2.ペーパークロマトグラフィーによる分析結果)
有効数字に注意
有効数字を見極めて、余計な計算をしすぎたり、精度が落ちたりしないように注意する。
有効数字のページも参照。
「感想」「反省」は書かなくてよい
どうしても感想や反省を書きたいときには、「感想」(または「反省」「感想と反省」など)という項目をつくって書くこと。考察の中に感想・反省は書かない。
考察はあくまで推論であるので、実験者の感想は求められていないことに注意すべきである。
考察をしっかり書く
実験レポートの要は考察にある。
考察では、観察された事実の科学的な意味づけや、実験の意義、実験からわかったこと、今後の展望などを書く。
実験がうまくいかなかった場合には、失敗の原因を分析して書くとよい。
スポンサードリンク
大学レポートの書き方 > 実験レポートの書き方