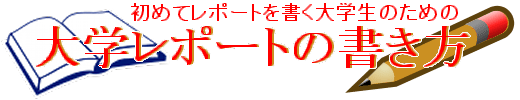Wikipedia(ウィキペディア)というサイトがあります。
日本語版:http://ja.wikipedia.org/
自然科学、人文科学、社会科学ほか、芸術、文化、サブカルチャーまで様々な情報を備えたフリー(無料)の百科事典です。
Googleで検索をしても、Wikipediaの記事がトップに来ることが多いので、この記事を読んでいるあなたもよく目にすることと思います。
実際、私もちょっとした調べものなどにWikipediaをよく使います。
しかし、Wikipediaの情報だけを参考にレポートを書くのは止めたほうが良いでしょう。
Wikipediaの記事のコピペは絶対ダメ
まったく知らない分野についてレポートを書け、と言われたら
「本を読むのも大変だし、Wikipediaの記事をコピペ(コピー&ペースト)で済ませちゃおう!」
と思いたくなるのが人情です(笑)
しかし、Wikipediaの記事は教員もチェックしていることが多く、コピペはすぐにバレてしまいます。
たとえ教員が記事自体をチェックしていなくても、複数の学生が似たような文章を書いていたら、教員は不審に思って検索してすぐにバレてしまうでしょう。
そして大多数の教員は、Wikipediaの記事のコピペに対して強い反感を持っています。
要は他人のレポートの丸写しですから、バレた時点でカンニングと同じようなものです。
「Wikipediaの丸写しをしてきた奴は問答無用に落とす」と明言する教員もありましたが、たとえ口には出さなくともほとんどの教員は同じ気持ちだと思います。
なので、Wikipediaの記事のコピペは絶対ダメです。
では参考文献として載せるくらいならどうなの?
コピペがダメだとしても、「Wikipediaの記事を参考文献として載せるくらいならどうなの?」と思うかもしれませんが
それもあまり良くありません。
ブログの中で参考URLとしてWikipediaの記事を載せるくらいなら問題ないのですが、
学術的なレポートの参考文献としてWikipediaの記事を使うのには色々と問題があるのです。
思いつく問題点として3つあります。(もっとあるかも知れません)
問題点1.情報の信頼性が低い
Wikipediaの記事は、基本的に匿名の投稿ですから、誰が書いたものなのか分かりません。
匿名で記事が書かれている、という点からすれば掲示板に書かれた情報と同じ、と言ってもいいくらいなのです。
誰が書いたのか分からない文章は信用しないのが学術的態度です。
問題点2.Wikipediaは三次資料である
資料は、どれだけ生データに近いかによって、一次資料、二次資料、三次資料などと分けられます。(分類は学問分野によって多少異なります)
自然科学の分野で言えば、実験データが一次資料、そのデータを学者がまとめて解釈などした論文が二次資料、そしてそれら学者の論文を参照してつくられるのがWikipediaなどの百科事典で三次資料と呼ばれます。
そして、論文やレポートを書くときにはできる限り生データ(一次資料、二次資料)にあたることが推奨されます。
特に出典の書かれていない三次資料はまったく価値が無いとも言われます。
問題点3.記事の正確性・厳密性
Wikipediaは非常に内容豊富な百科事典ではありますが、その正確性・厳密性はどうしても専門書に劣ります。
大学の教員レベルから見ると「ちょっと、これどうなの?」と思うような内容も書かれていることがあるとか。
そのため、たとえ教員がWikipediaをチェックしていなくても、査読を入れることで減点されてしまうこともあるでしょう。
結論:Wikipediaはあくまで「参照資料」に
Wikipediaは非常に便利ですが、学術用のレポートに使う資料としては、いろいろと問題があります。
ちょっとした調べ物のときに参照するくらいの使用にとどめて、レポートに書くときにはWikipediaで参照されている一次資料、二次資料にあたるのが良いでしょう。
参考URL:レポートとWikipedia